フリーランスか雇用か?ウェブ制作で自分に合った働き方を選ぶヒント
フリーランスか雇用か?ウェブ制作で自分に合った働き方を選ぶヒント
Message box 公開日:2025.09.04 更新日:2025.10.21
近年、ウェブ制作の現場では「雇用」と「フリーランス」という働き方が共存し、それぞれが重要な役割を担っています。どちらを選ぶかは、収入の安定性、働く場所の自由、ライフスタイルとの相性など、人によって最適な選択が異なります。こちらでは、雇用とフリーランスの違いや業界の現状、今後の働き方のヒントを通じて、自分に合った働き方を見つけるための考え方を紹介します。
Web制作におけるフリーランスと雇用の違い
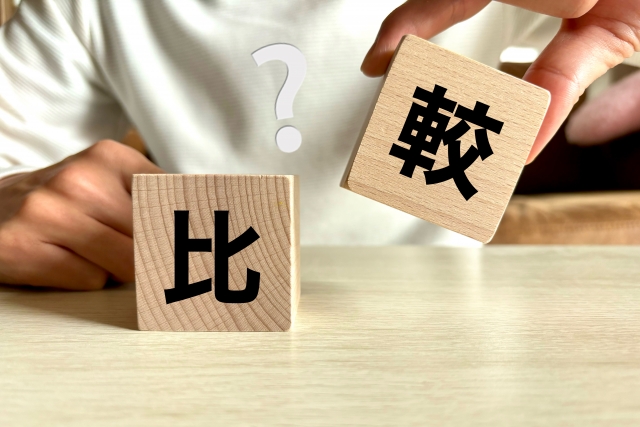
Web制作の現場では、正社員や契約社員といった「雇用」だけでなく、「フリーランス」として働く人も多く存在します。それぞれの働き方には特徴があり、自分に合った選択をすることが重要です。
まず雇用形態の違いですが、雇用とは企業に所属して働く形で、正社員・契約社員・派遣社員などが含まれます。一方、フリーランスは企業に所属せず、個人事業主として案件ごとに契約を結んで働くスタイルです。多くの場合、業務委託契約という形でクライアントと取引します。
仕事の進め方にも違いがあります。雇用されている場合、上司やディレクターの指示に従って業務を進める「指揮命令関係」がありますが、フリーランスはあくまで成果に対する契約のため、仕事内容やスケジュールの進め方にある程度自由があります。
働き方の自由度も大きな違いのひとつです。雇用されている場合、出勤時間や勤務場所(主にオフィス)は企業によって定められており、柔軟性は限られます。対してフリーランスは、働く時間や場所を自分で決められるため、リモートワークやワーケーションとの相性が良いです。
給与面でも違いが明確です。雇用されている場合は月給制や年俸制が一般的で、毎月安定した収入が得られます。フリーランスは案件単位で報酬が決まるため、収入が月によって大きく変動することもあります。
また、福利厚生や社会保障も異なります。雇用されている場合は健康保険や厚生年金、雇用保険などが企業を通じて整備されていますが、フリーランスは自分で国民健康保険や国民年金に加入し、すべて自己責任で管理する必要があります。
それぞれのメリット・デメリットをまとめると、雇用は安定性があり、福利厚生も充実している一方で、自由度はやや低めです。フリーランスは時間や働く場所の自由がある代わりに、収入や仕事の確保、税金管理など多くのことを自分でこなす必要があります。
安定を重視したい人やチームで働きたい人には雇用が向いており、自由な働き方を求める人や自己管理が得意な人にはフリーランスが適しているでしょう。
ウェブ制作業界における働き方の現状
ウェブ制作業界は、案件ごとにチームを組んで進行するプロジェクトベースの仕事が多いのが特徴です。明確な納期が設定されていることがほとんどで、それに向けて効率よく作業を進める必要があります。また、すべてを社内で完結させるのではなく、一部業務を外注するケースも多く、フリーランスの活躍の場が広がっています。
特に小規模の制作会社やスタートアップでは、固定の人材を雇うよりも、必要なタイミングで外部人材を活用する柔軟なスタイルが一般的です。専門性の高いスキルを持ったフリーランスに業務を委託することで、コストを抑えながらクオリティを確保できるという利点があります。
フリーランスが増えている背景には、制作ツールやコミュニケーションツールの進化があります。ブラウザ上で共同作業ができるFigmaや、進捗管理ツールのNotion、Slackなどの普及により、場所を問わずチーム作業が可能になりました。また、**SNSやクラウドソーシングサービス(例:ココナラ、クラウドワークス)**を通じて案件を獲得することも一般的になり、個人でも仕事を見つけやすくなっています。
企業側も、すべてを社員でまかなうのではなく、雇用とフリーランスをうまく使い分けるようになっています。たとえば、デザインやコーディングといった実作業は外注し、ディレクションやクライアント対応は社内スタッフが担当するといった形です。
また、職種によって働き方の傾向も異なります。デザイナーやコーダーはフリーランスでも活動しやすい一方で、クライアントとの調整が多いディレクターやプロジェクトマネージャーは、社内に常駐しているケースが多いです。
このように、ウェブ制作業界では柔軟な人材活用が進んでおり、スキルやライフスタイルに応じて多様な働き方が選べるようになっています。
ウェブ制作の未来と多様化する働き方
近年、「副業OK時代」の到来により、会社員であっても業務時間外に別の仕事を請け負う「複業」が一般化してきました。ウェブ制作はPC一つで完結する仕事が多いため、副業やフリーランスとの相性が非常に良く、本業と並行して案件を受ける人も増えています。
その流れの中で、企業とフリーランスの間にあるような中間的な働き方も注目されています。たとえば、特定の企業と継続的に契約する「業務委託」や、複数の企業と並行して関わる「パラレルワーク」、フリーランス同士がチームを組んで案件に取り組む「ギルド型組織」など、柔軟で多様なスタイルが生まれています。
また、今後の働き方を語る上で無視できないのが「AIやノーコードツールの進化」です。画像生成や文章作成をAIが補助し、WebflowやSTUDIOなどのノーコードツールを使えば、コーディングの知識がなくてもWebサイトを制作できるようになりました。今後は「作るスキル」だけでなく、「どう設計するか」「何を提案するか」といった上流工程のスキルがより重要になるでしょう。
フリーランスとして長く働くためには、単にスキルがあるだけでは不十分です。魅力的なポートフォリオを作成して自分の強みを発信したり、クライアントとの交渉力を身につけて適正な報酬を得たり、継続案件につなげる信頼関係の構築が不可欠です。また、学び続ける姿勢や、新しいツールへの柔軟な対応力も大きな武器になります。
最後に、自分に合った働き方を見つけるためには、「何を大事にしたいのか(収入・時間・自由・安定)」を見極め、短期と長期のキャリア設計を考えることが大切です。雇用かフリーランスかという二択にとらわれず、自分のライフスタイルや価値観に合った「働き方の形」を模索する時代が、すでに始まっています。
まとめ
ウェブ制作業界では、雇用とフリーランスという多様な働き方が存在し、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。業界はプロジェクトベースで動き、納期管理が重視される中で、外注や業務委託といった柔軟な人材活用が一般的になっています。特にスキルの高いフリーランスは、小規模事業者やスタートアップを中心に重宝されています。
近年は「副業OK」の流れやクラウドソーシング、SNSを通じた案件獲得が一般化し、フリーランス人口も拡大。また、ノーコードツールやAI技術の進化により、制作工程そのものも大きく変わりつつあります。これからは単なる「作業者」ではなく、提案力や設計力を持つ人材がより求められるでしょう。
自分に合った働き方を選ぶには、収入・自由・安定など、自分が何を重視したいのかを明確にし、将来を見据えたキャリア設計をすることが大切です
-
ネット系・スキル活用・現場仕事まで!目的別でわかる副業ガイド
-
未経験からでも安心!ジャンル別にわかる在宅の仕事完全ガイド
-
副業に最適な在宅ライター入門
-
本業なしでも始める在宅ライティング
-
副業ウェブデザインの魅力と実践法
-
在宅で始める!ウェブデザイン副業の完全ガイド
-
副業・在宅ワーク入門!仕事の探し方と成功のコツ
-
在宅で出来る仕事の探し方:未経験から始めるための完全ガイド
-
フリーランスで働きたい!自分に合う仕事の見つけ方と主な職種の仕事内容
-
ウェブデザイナーの仕事に向いている人は?仕事内容と求められるスキル
-
フリーランスライターの仕事内容と活躍の場を広げるために必要なこと
-
プログラマーのためのフリーランス仕事受注ガイド|案件獲得から安定収入まで
-
主婦でも起業は可能?経験を活かして成功するための実践ガイド
-
起業のベストタイミングはいつ?成功を引き寄せる「起業」の始め方
-
起業しやすい人気の業種と失敗しないための秘訣